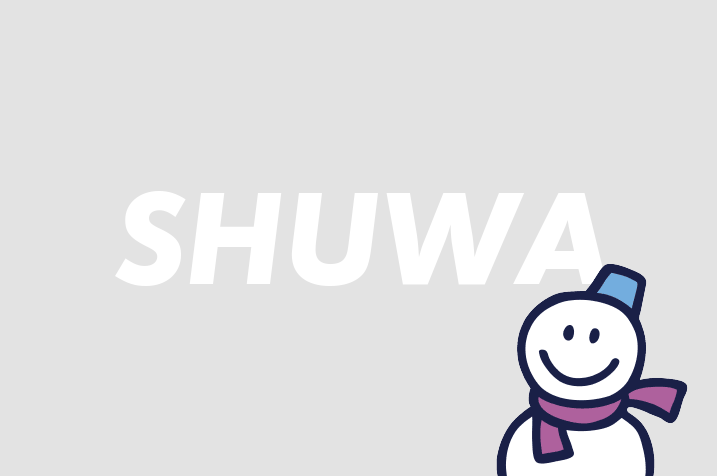ゆでガエル現象

興味深い雑誌記事がありましたので、抜粋して朝礼の話題としてお伝えします。
危機を認識しつつも放置する『ゆでガエル現象』の怖さ
『熱湯にカエルを入れるとそのカエルは驚いてすぐに脱出します。一方、水の中にカエルを入れて徐々に温めていった場合、危険を察知することが遅れてしまい、そのカエルは死んでしまいます。』
この『ゆでガエル現象』は、書籍などでよく紹介されていますし、ビジネス系のセミナーで話される方も多いので、ご存知の方もたくさんいらっしゃるでしょう。
例えばある会社で・・・。
「まもなく景気は上向くだろうから、もう少し辛抱すれば大丈夫」「問題が発生していることはわかっているんだけど、社員全員に関係する話でもないからそんなに事を荒立てなくても良いですよ」
これは、すでに『危機』が迫っていることを認識しているのにもかかわらず、その『危機』に対して向き合うことをせずに放置している事例です。結果的に、『ゆでガエル』と同じ末路を迎えることになることを示唆しています。現在、話題となっている大相撲八百長問題も、まさにこの『ゆでガエル現象』を思い出させる話である。
この間の朝礼でもお話をしましたが、大相撲での出来事、暴力事件・死亡事件・賭博事件・大麻事件と様々な問題があった。さらに今回は屋台骨を揺らしかねない八百長問題まで。なぜ、このタイミングになるまで八百長問題は解決されなかったか?
「春場所中止」「力士の処分」など『小手先療法』では解決しない組織の問題 大相撲の八百長は、以前から週刊誌などを中心に多くのマスコミで取り上げられてきた問題です。今回、相撲協会も「春場所の開催を中止する」という苦渋の決断をし、「徹底的に調査して膿を出し切る」という覚悟を示していますが、それが「関わった力士を全て見つけ出して重い処分を下す」ということだけだとすると、抜本的な問題解決には至らないような気がします。
マスコミの連日の報道でも、、大相撲の給料格差が問題に取り上げています。
十両(年収約1600万円)と幕下(年収約90万円)関取の年収例である。「強い者が偉い」プロの世界では当たり前のようですが、数字的にも明らかなので言うまでもないですが、この制度において最も気になるのが、十両と幕下の大きすぎる格差です。確かに、昔に作られたこの制度が悪いという話ではありませんが、長年運用されるなかで制度疲労を起こしていると感じます。大相撲の世界自身が、時代の変化対応できていない状態ではないでしょうか?
よって、八百長問題を抜本的に解決しようとするのであれば、この制度にメスを入れることも必要であると思います。もうひとつ気になることが『お客さま目線』欠落ではないでしょうか?そもそも、日本相撲協会は財団法人として認可されており、税制面も優遇されていることから、いわゆる経営上はとても裕福で経営の心配など、ほとんど気にしていない組織だそうです。本来のビジネスは、真剣勝負をお客さまが、高いお金を払ってでも観戦をして貰い、利益を出して税金を払うモデルである。
感動の取組を観戦しにきてくれるいるから、スポンサーもつき、だからこそ協会は場所を運営でき、力士は報酬が貰える、スタイルが本来である。様々な問題を見てみると、とてもお客さまを最優先に考えているようには感じられないのです。それは、言い過ぎでしょうか?
相撲協会も、もう一度、原点に戻り“お客さま目線”で「何がお客さまが期待をしているのか」を再定義した上で、力士たちも徹底的に教育することが最重要だと思います。当然、ファンとしては「稽古で鍛え上げた肉体で、力士同士の真剣勝負を見てみたい!」と感じるのは皆さんも同じではないでしょうか。『ゆでガエル現象』は危機に対応できなかった例を示す話ですが、「真の問題を認識した上での解決策」と「お客さま目線を植えつけること」である。それは、相撲協会だけでは無い問題であり、シューワでも日々色々な問題が起こっている中で瞬時にどのような対処をするのか!
問題の単なる小手先での解決策ではなく!本質の問題解決力と俊敏性をつけて行かなくてはいけない。今回の問題で感じた事は、マンネリ化は怖さや変化に対する感度を鈍らせて、組織の活性を減衰させる。企業も個人も同じだが、この厳しい時代に生き延びていくには、常に変化を素早く認識するアンテナが必要である。シューワ実践二十魂にもある。時代に変化に対応する為に、準備・段取り・計画・報告・フォロー・反省の実行の日々反復が極めて重要であることを教えられた。
一つの商品でも、変化・革新が必要であり、それを怠ると衰退を余儀なくされる。『失敗しないのは前進していないこと。つまずかないのは歩いていないこと』を肝に銘じ、大胆にかつアグレッシブに前進して行きましょう!
最後に
今週はチャールズ・ダーウィン(イギリスの自然科学者)の言葉にたいへん感銘うけた。
- 生き残るのは、種の中で最も強い者ではない。
- 種の中で最も知力の優れた者でもない。
- 生き残るのは、最も「変化」に適応する者である。
ゆでガエル現象に陥っているかのチェックリスト
- 上から降りてくる仕事をこなしている。
- 変化もなく、平凡で心地良い状態である。
- 興奮することもなく、新たに大きな挑戦もない。 熱中することもない。
- 人生に対する特に大きな目標もない。
そして、常に組織にいる人間が感度と好奇心を旺盛にしていなければならないと言っています。