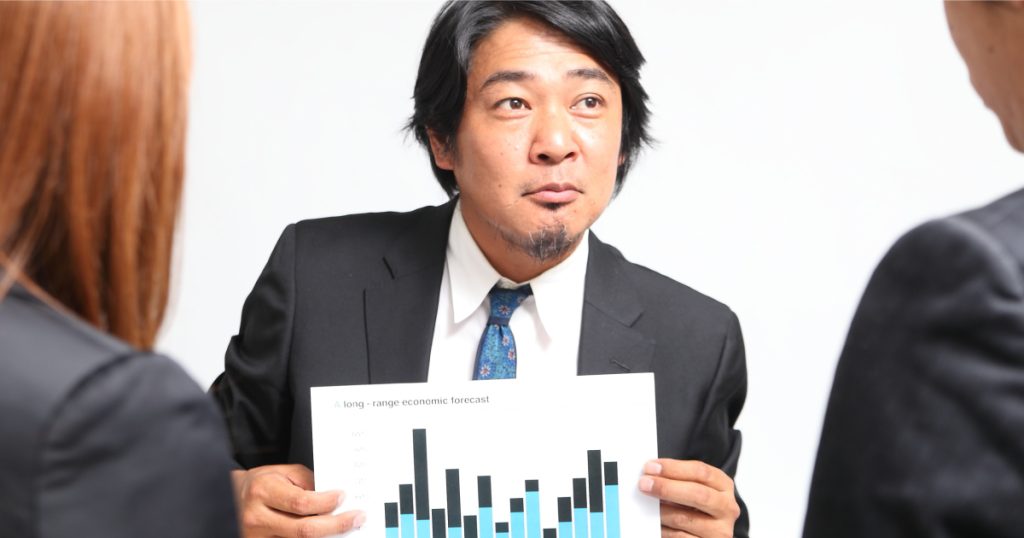自助・共助・公序

今週の1月17日は「阪神淡路大震災」から24年目となりました。
1995年1月17日午前5時46分、淡路島北部を震源としてM7.3、最大震度7の地震が発生。
この大震災により6434人の尊い命が失われました。
あれから24年の月日が経ちますが、つい昨日のようでもあります。
当時を振り返りますと大阪南部・堺でも下から突き上げてくる振動があり、
大きな大地震が起こった事を今でも鮮明に記憶にしています。
そして、早朝にテレビをつけたら、その大震災の映像ばかりでした。
当時はインターナットもそれほどなく、被災現場の状況が分からず、心配や不安ばかりが先行していました。
阪神高速神戸線の道路が倒れた映像が今でも心に刺さっています。
あの平成8年最悪の大震災の際に、当時グリーンスタジアム神戸の近くにあった無数の仮設住宅に当時は禁止をされていましたが、
ストーブと灯油を運んだ経験を思い出します。
この応援が今のBCP活動のスタートと言っても過言ではありません。
様々な辛い体験や経験から、多くを学んだと思います。
その体験や経験を活かすことが、亡くなられた方々への一番の供養だと思います。
亡くなられた方々のご冥福を祈ると共にその大震災から復興された方々に、心から敬服いたします。
年末にある大手企業の幹部の方から、これからの時代は「自助・共助・公序」の考えがとても重要であると教えて頂きました。
・自助とは、自ら(家族も含む)の命は自らが守ること、または備えること
・共助とは、近隣が互いに助け合って地域を守ること、または備えること
・公助とは、役所をはじめ警察・消防・ライフラインを支える各社による応急・復旧対策活動を指します。
この考えは特に阪神淡路大震災以降に注目されるようになり、東日本大震災で改めて理解が求められるようになったそうです。
そして、各項目の重要度は、自助7割、共助2割、公助1割とも言われています。
これは、他人や役所には、救助・援助を期待できないことを意味します。
さらに、他人が当てにならないとすれば、如何に日頃から”自助=自衛”を考えながらの訓練や備えが大切だと感じます。
近年の複数災害からのBCP(事業継続計画)への自助、共助への関心を深め啓蒙活動に取り組みたいと思っております。
今までの震災=災害=地震と考えていましたが、災害のカテゴリーが考え方が変わりました。
「事業継続計画」日本BCP株式会社にとっても一つの転機になったように思います。
これから、大阪では世界的注目行事であるビックプロジェクトG20・IR・大阪万博などが立て続けに行われます。
2018年の訪日外国人客数が、同日時点で3000万人を突破したとの事ですので尚更に災害対応が必要です。
シューワグループと日本BCP株式会社が掲げる、
総合防災・減災企業を目指して、”ありがとうの言葉”と安心してを暮らせる”ライフライン企業”を目指して行きましょう!