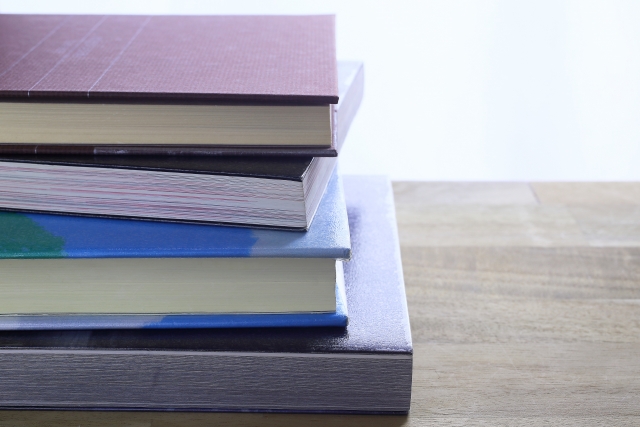危機管理

みなさんの週報でも、2週に渡って日大アメフト選手の悪質タックルについてたくさんコメントが載っていましたが。
ネットニュースやTVのワイドショーでは森友・加計問題に始り、人気タレントによる強制わいせつ事件、元財務次官のセクハラ疑惑、など著名人や組織、企業の不祥事が絶えません。
問題発覚後の対応によっては、日大のようにさらなる炎上を招き、収拾がつかなくなるケースもあります。
最近は不祥事そのものよりその後の対応が大きく取り上げられる傾向にあるようです。不祥事後の対応はどうあるべきか。
今回、吉本興業で芸人らのトラブルやスキャンダルの対応策を一手に引き受け、退社後は起業して「謝罪マスター」としてコンサルティングを行う竹中功氏の正しい謝り方という記事を見つけましたのでご紹介したいと思います。
■大事なのは反省と再発防止策だけ 内輪の話は余計
――人気グループの元メンバー・事件後の会見は
「厳しく言うと準備不足を感じました。本人が謝罪の意味を混乱してしまったのかもしれません。
『戻りたい』と言いたくなる気持ちも分かるが、伝えるべきポイントはそこじゃない。
「大事なことはやってしまったことの反省と再発防止策の2つです。言い訳に何の意味もありません。
例えば芸人が遅刻したらどうなるか。電車が遅れたと言っても、吉本の場合は通用しません。
運がなかったね、ほなさよなら』で終わり。なぜなら別の人に迷惑をかけているんです。
遅れてしまったことだけが大事。もう一つ重要なことは再発防止策。
応援してもらうためにも再発防止ってとても大切です。謝罪は再発防止まで含めてセットなんです」
そして■許すカードは相手が持っている
「お笑いタレントのたむらけんじさんが副業の焼肉店で食中毒を起こし、1人が入院するという事件がありました。
このときの会見は、あくまでメディアを通して、腹痛を起こしてしまったお客さんに謝ることが一番大事だということを本人にも確認してもらいました。
まず苦痛を与えてしまったお客さん、心配をかけたご家族に謝る。そしてファンに対して、心配かけてすみません。その次に関係者の皆様すみません、というのが謝罪の順番です」
「僕がくぎを刺したのは、最後に『吉本の芸人ならびに社員の皆さんすみません』という言葉が出てきそうだと思ったので、それは内輪の話だからここで言う台詞じゃない、ということ。
時々そういうことを言う芸能人がいたんですよね。でも社員に謝るのは、後で会社とか楽屋に行って直接言ったらいいんですよ」
「謝罪シナリオじゃないですけど、誰に何を謝るのか、どこを強調して言うかをたむらさんはよくわかってくれた。
よくわかってくれたというのは、よく反省しているということなんです。彼は自分の言葉で反省と再発防止策を説明しました。
「怒り(イカリ)を反対から読むと理解(リカイ)になります。怒りをいかに理解に変えるか、それが達成された時に初めて謝罪が成功したといえます。
公人の不祥事でも「大臣が『セクハラ罪という罪はない』と言っていましたが、そんな話じゃない。世の中からズレている。
社会性が低いってことです。人の痛みとか喜びがリアルでわからない。被害者は名乗り出ろとか、出られない人の立場の弱さを理解していない。
相手の側に立つという、常識が抜け落ちている」本来は立場が高い人ほど、相手の気持ちに敏感にならないといけないと思います」
そして最後に危機管理
吉本興業ではリスク管理チームというのがあり芸人に対してもコンプライアンス研修があります。
劇場で500人ぐらいの芸人に話すなど、毎年、数千人に話してきました。
大御所は研修なんて出てくれませんから楽屋まで押しかけましたよ。
「面倒に思われることもありますが、実際にコンプライアンス違反により契約解除されたりする悪い例が目の前にあるから、緊張感を与えることはできると思うんです。
危機管理はこういう対話の積み重ねです」と仰っています。
ここからは私の意見です。私は管理業務をしているという事もあり事故報告書を扱う事があります。
報告書の中に「同じミスを起さないよう気をつけます」や「次からは注意して作業します」という言葉をよく目にします。
その際にいつも思う事が、それはあなたの反省で再発防止策では無いという事です。
みんな作業する時には気をつけて、注意して行っているはずです。それでもミスするから事故なんです。
具体的な原因と事故が発生しない為の対策が必要です。そこまで書いて事故報告書だと思っています。
仕事中の事故には命に係わるものから、連絡や報告漏れといったものまで様々ですがなにが会社の危機に繋がるかはわかりません。
竹中さんが仰っている「危機管理とは対話の積み重ね」というように発生したミスや事故が再発しないように事前に対策を周知させ積み重ねていく事が危機を招かない為の管理だと思います。
ぜひ皆さんも身近で起きる事故やミスをそこで終わらせずその先の危機管理について業務にあたっていただければと思います。