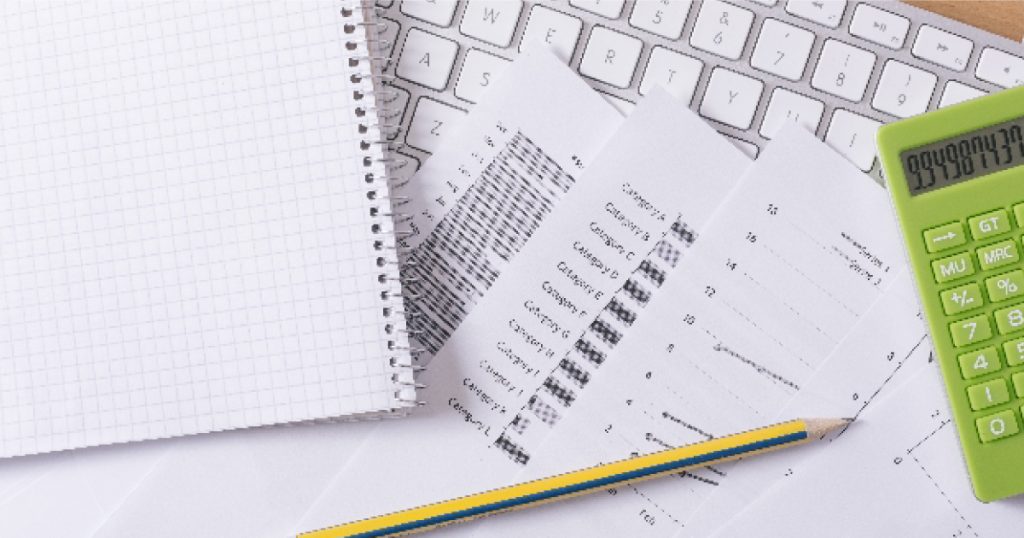人生と経営における六波羅蜜

今月も稲盛塾長「京セラフィロソフィ」を皆さんと共に輪読して学びましょう。
そして、シューワグループ全従業員・物心両面の幸福実現の為に真摯に向き合いながら実践したいと思います。
シンプルかつ直球の稲盛塾長の”魂の言葉”は今回も胸に熱く刺さりました。
旧盛和塾(大和)にて、諸先輩が選んでくださった稲盛塾長DVD「人生と経営における六波羅蜜」を拝見させて頂きました。
【今月のキーワード】は 『善きことを思い、善きことを実行』・・・・。皆さんと共にど真剣に学んで行きましょう!
《出典 『致知』2022年05月16日.参照》
—–京セラやKDDIを創業しそれぞれ大企業に育て上げ、「絶対不可能」と言われたJALの経営再建にあたっては僅か2年8か月で再上場へと導いた稲盛和夫氏。
挫折続きだったという稲盛氏はいかにして運命を好転させ、経営の道を切り拓いてこられたのでしょうか。
■善きことを思い、善きことを実行するために
〈稲盛〉
人生には確かに運命というものが存在します。
その運命を自分で知ることはできませんが、自分が辿っていく人生というものは生まれた時から決められているものだと思います。
私の前半生がそうであったように、挫折続きで、過酷な人生が運命で決められていることもあるかもしれません。
しかし、そのような人生の節々で、善きことを思い、善きことを実行していけば、運命はよい方向へと変わっていくのです。
逆に人生の節々で悪しきことを思い、悪しきことを実行すれば、運命は悪い方向へと曲がっていくのだろうと思います。
では、いかに善きことに努めるか。
私はお釈迦様が説かれている「六波羅蜜(ろくはらみつ)」という6つの修行がまさにそのための方法ではないかと考えております。
つまりお釈迦様が魂を磨き、心を高め、悟りの境地に到達するための修行として説いておられることが、まさしく私が申し上げた善きことに努めるということと同じことではないかと思っています。
■「六波羅蜜」が教えてくれるもの
1番目は「布施」です。
自分がいまあることに感謝をし、他に善かれかしと願い他人様のために何かをして差し上げることです。
その思いやりの心、優しい心を持って世のため、人のために尽くすということ、施しをするということが「布施」の意味です。
2番目は「持戒」です。
戒律を守るということであります。
人間としてしてはならないことを定めた戒めをひたすらに守っていくということです。
言い換えれば、人間として何が正しいのかを問い、その正しいことを貫き、そしてしてはならないことはしないということ。
それが「持戒」、戒を守るということであります。
3番目は「精進」です。
人は生きていくためには働かなければなりません。
働くということは厳然たる人生の鉄則であり、お釈迦様は、ただ一所懸命に誰にも負けない努力で働きなさいとおっしゃっています。
それが「精進」であるとおっしゃっているのです。
4番目は「忍辱」です。
恥を忍びなさいということ、苦しいことや辛いことも耐え忍びなさいということであります。
人生は波瀾万丈であり、いまは幸せに思えても、いつ何どき苦難が押し寄せてくるか分かりません。
その厳しい試練を耐え忍んでいくことが大切だということを教えていただいているのです。
5番目は「禅定」です。
心を静かにすることです。荒々しい心のままでは心を高めることはできません。
多忙な毎日を送る中でも心を静めることに努めなさいとお釈迦様は説いておられます。
6番目は「智慧」です。
ここまでの5つの修行に日々懸命に努めていくことで悟りの境地、つまり偉大な仏の智慧に至ることができると言われております。
先に申し上げましたように私は25~26歳の時に過去を振り返り、素晴らしい出会いがなければいまの自分はなかったことに気づき、感謝の念が芽生えてまいりました。
そしてその時から、世のため、人のために尽くすために誰にも負けない努力を払い、人間として正しいことを貫き、試練に耐え抜き、時に心静かに反省を繰り返してまいりました。
そのような生き方が奇しくもお釈迦様が説かれた六波羅蜜の修行に通じていたわけです。
だからこそ苦難続きであった私の人生の歯車が逆回転を始め、大きく開けていったのだと思います。—–
今回のDVDの中で、稲盛塾長曰く、「六波羅蜜」は難しくないと仰っていましたが、私のような凡人にはとても難しかったです。
塾長は「六波羅蜜」の中で真っ先に「精進」挙げられていました。
「精進してまいります」は、ビジネスシーンでよく耳にする言葉ですね。
「頑張ります」や「努力します」と言った前向きな気持ちを丁寧に敬語で表現した言葉です。
これまでの長い間の社会人生活で、旧盛和塾(大和)に入塾するまでは、正直に「六波羅蜜」ような考え方になった事はありませんでした。
いままでは、商売ですから、いかにたくさん売り上げを上げて利益を上げるか?そして、収益を上げ分配して会社を大きくする。
まさに、考え方の基本が狩猟型民族的で稼業的な考え方でした。
しかしながら、長い期間を見た”素晴らしい人生”を送るためには、この様な考え方が重要だと教えてくださっています。
そして、二宮尊徳のように、農業の仕事を通じて、素晴らしい人間性の悟りを開く境地に至るまで自身を高めることが必要とのことです。
そして、旧盛和塾(大和)では塾長が六波羅蜜を噛み砕いて、【6つの精進】として学びとして貰っています。
ちょうど4月度のお題も「6つの精進」でしたので入りやすいと思います。
■6つの精進
1.誰にも負けない努力をする
2.謙虚にして驕らず
3.毎日の反省
4.生きていることに感謝する
5.善行、利他行を積む
6.感性的な悩みをしない
・人間として成功するための「6つの精進」
人生と仕事に悩んだ時には、この”6つの精進”の1~5番までをもう一度見直してみると良いそうです。
見直した時に、自分は全ての項目をしっかり意識している!という方は、6番のように悩む必要は無いということです。
「6つの精進」、これが自分の背骨となるよう、自分が生きていく姿に自然になっていくよう、これから先も常に唱え、意識して行動を心掛けていきしょう!
「不平不満を言って人生が豊かになることなど無い。勿論、成功した人などいない。」善きことを思い、善きことを実行することで、プラス思考が重要かを以前にもお聞きしました。
自分自身の心、魂がどれだけ浄化されて、高まっていけているのか?
まだまだですが、これから先もしっかりとこの塾長の言葉を忘れずにやっていこうと思っています。
日々、仕事を通じて、自分を見失わないように心を高めて経営を伸ばす事が重要です。
そして、ひとりの人間として、日々の行動を見直す真摯な心を持った、自分自身のしっかりとした人生の舵取りが必要だと感じました。
さあ、長いゴールデンウィークも終わりました。
しっかりと「六波羅蜜」と「6つの精進」を学び、反省と自戒の念を含めて考え方をしっかりと持っていきましょう!