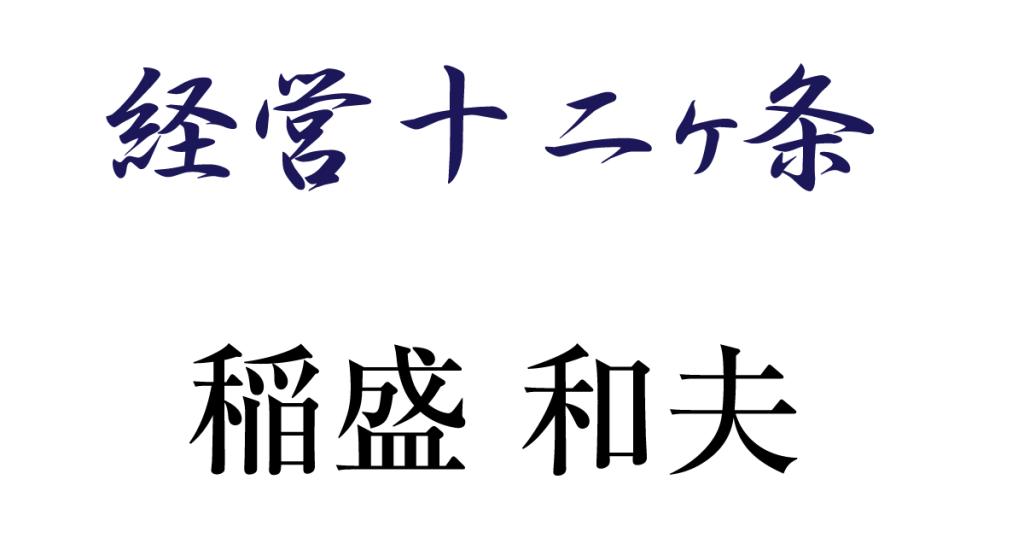「日本の資本主義の父」

天命に身を委ね
コツコツとくじけず勉強する
今日は、今旬のお話をしたいと思います。
最近、渋沢栄一に関する話題が尽きませんが、皆さんは昔から渋沢栄一の事を知ってましたか?
私は大河ドラマで最近見て知ったし、オーディブルを聞かして頂いて知ったくらいです。この度紙幣になる事で知った人もいるでしょう。
これまでも渋沢は紙幣の顔として何度も候補になりましたが、当時は偽札予防ということもあり、「髭がない」という理由で実現しなかったと言うエピソードがあります。
それでは、少し渋沢栄一に付いて調べた事をお話ししましょう。
それにしてもなぜ今、渋沢がこれほど脚光を浴びているのでしょうか?
理由は混迷する時代の中で自らの志を貫いた渋沢の生き方にあります。
渋沢が約500もの企業の設立や運営に関わったことはよく知られていますが、それ以上に注目すべきは約60とも言われる教育機関や社会公共事業の支援したことや、悪化の一途を辿っていた日米関係を改善するために高齢の身で幾度も渡米するなど民間外交に力を注いだことです。
「日本の資本主義の父」としてこうした活動が認められ、ノーベル平和賞の候補に2度も選ばれています。ノーベル賞は採ってないんですね・・・
渋沢ほど世界に目を向けた活動をする一方で、弱い立場の人たちに目を向け、かつそれを生涯実行し続けた企業家は世界でもまれな存在と言えます。
偉大な企業家にして、偉大な社会事業家でもあった渋沢は自分の人生を自らが設立に関わった富岡製糸場が扱っていた蚕(かいこ)の繭(まゆ)にたとえてこう表現しています。
「自分の身の上は、初めは卵だったが、あたかも脱皮と活動休止期を4度も繰り返し、それから繭(まゆ)になって蛾(が)になり、再び卵を産み落とすようなありさまで、5年間にちょうど4回ばかり変化しています」と言っています。
渋沢は1840年、今の埼玉県深谷市の豊かな農家に生まれています。
幼い頃から古典を学び、12歳の頃からは剣術の稽古にも励んでいます。
学問が好きで、剣術にも優れた才能を発揮する少年でしたが、14、5歳の頃からは「そろそろ農業や商売にも身を入れてもらわなければ困る」という父親の教えもあり、若くして商売にも優れた才覚を発揮しています。
渋沢はこのまま農家の跡取りとして人生を送ることになったはずですが、黒船来航(1853年)や桜田門外の変(1860年)といった社会を揺るがすような出来事が相次いだことで渋沢も国元を離れて以降は志を立てたつもりが思惑がはずれ、思いもかけない人生を送ることになりました。
渋沢が最初に目指したのは幕府打倒でしたがあえなく計画は中止、身を隠すために京へ向かったものの、なぜか本来は敵である一橋家に士官することになります。
ここまでが、NHK大河ドラマで夕べまでやってたところです。
渋沢の逆境への対処法は、その逆境は「人のつくった逆境」か「人にはどうしようもない逆境」であるかを見極めたうえでどうするかを考えるというものです。
自分に責任のある逆境は反省するほかありませんが、歴史の転換点のような人にはどうしようもい逆境にあっては「天命に身を委(ゆだ)ね、腰をすえて来たるべき運命を持ちながらコツコツとくじけず勉強する」ほかありません。
最も大切にしたのが「道徳に基づいた経営」であり、「自分のことよりもまず社会を第一に考える姿勢」でした。
資本主義はとかく弱肉強食界であり、格差を当然のように生みますが、渋沢が目指したのはそこで生まれる弱者に対しても優しい目を持つ資本主義でした。コロナ過のために、多くの人や企業が厳しい状況に追い込まれています。
まさに「人にはどうしようもない逆境」にあるわけですが、そんな時代だからこそ渋沢の生き方を知り、その言葉に触れることは生きる勇気につながると思います。
シューワの社員が一つの目標に向かって一致団結しこのコロナ過を乗り越えていきましょう。