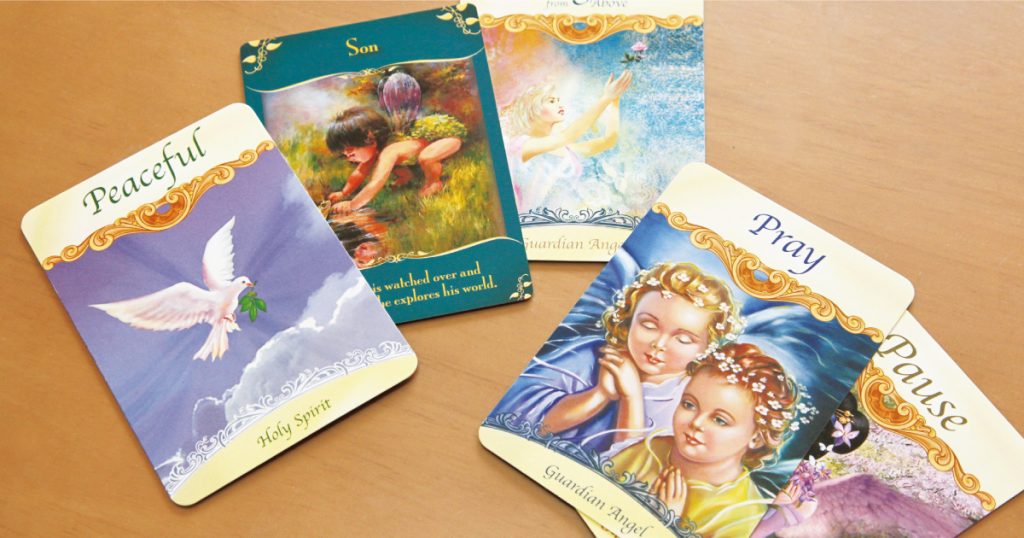「ご先祖様に感謝」

先週15日は75回目の終戦記念日でした。
先の戦争では一般市民を含めて日本人の約300万人が亡くなりました。
長い日本の歴史において、最も悲惨な出来事だと言えるでしょう!!
現代の豊かな日本があるのも、先人の想像を絶する努力の結晶や祖先の方々が有り今があると思います。
今週は「お盆」について考えてみたいと思います。
今年は、コロナの影響があり海外旅行も前年比99.7%ダウンとの報道があり、まさに自粛の夏となりました。
年初からまさにコロナ一色です。
大企業や公務員には、お盆休暇の概念はありません。
ベンチャー企業であるシューワグループでは、毎年お盆時期に数日の連休を取り入れています。
今年はいつものお盆休みと異なり、大阪南部である当社でも、盆踊りや花火大会、だんじり祭りまでと様々なものに規制や自粛がなされています。
こんな寂しい「お盆」だからこそ、大切な「ご先祖様に感謝」しながら、今やれることをひとつづつ感謝をしながら行動をしたいと思います。
「お盆」とは、夏の時期にご先祖様をお迎えして一緒に過ごすという日本に古くからある年中行事のひとつですが、その起源や語源についてご存知でしょうか?
なぜ「お盆」というのか、どんな歴史があるのかを調べてみました。
【 お盆の歴史 】
お盆は正式には盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言い、インドのサンスクリット語が語源。
日本で最初にお盆の儀式が行われたのは606年のこと。
推古天皇が開いた「推古天皇十四年七月十五日斎会」という会でした。
8世紀頃からは夏に先祖供養をする習慣が貴族や僧侶、武家などの上流階級の間に広まりました。
江戸時代になると庶民にもお盆が浸透し、お盆に仏壇や提灯をともす家が増えていきました。
日本では「お盆」、キリスト教圏では「イースター」、台湾では「清明節、」ラテンアメリカ諸国では「死者の日」など、有名なお祭が世界各国にあります。
考え方や形は違えど、すべて「ご先祖様の供養」という点では共通していますね。
8月13日から16日はお盆。ご先祖様の霊があの世からこの世の家族のもとへと帰ってくる期間です。
お盆にはご先祖様を供養し、ご先祖様に感謝の気持ちを示し徳を積むことが開運への第一歩だそうです。
お盆にはご先祖様に感謝する機会を作ってお墓参りに行って手を合わせたり、お仏壇をきれいにしてご先祖様をお迎えする準備をしたり、お盆は感謝の気持ちを持ってご先祖様と向き合いましょう。
シューワ実践二十魂の「感謝の気持ちを忘れるな!」ではありませんが、無いものねだりをするよりも、今与えられていることに「感謝」の気持ちを持てる人になりたいものですね。
当たり前ですが父、母、祖父、祖母...先祖がいての我々です。
今、自分自身の全ての肉体の血や細胞の結晶はご先祖様によって形成されているとご先祖様に感謝をしないではいられません!
そして、もっとも簡単に出来るご先祖様に感謝する大切な方法が「お墓参り」ですね。
お墓の前で手を合わせて「健康で家族みんなが無事でいること」「ご先祖様のお陰で生かされている」ことに感謝する。
「ありがとう」⇒「有難う」⇒「有り難い」と感謝しているとさらに感謝をしないではいられないような良いことが、良いスパイラルとなって良い循環になると思います。
ご先祖が精一杯生きてこられたから、私たちがこうして日々を過ごす事が出来ます。
そして、地域で共に頑張っている人達の助けがあってこそと、改めて感謝をしています。
企業理念の「ありがとうの言葉を世界一集める」企業としても「とても意味のある!ご先祖様に感謝」だと感じます。
つかの間の休暇ではありますが、「感謝」の心を持って心身ともにリフレッシュできるよう過ごしてください。