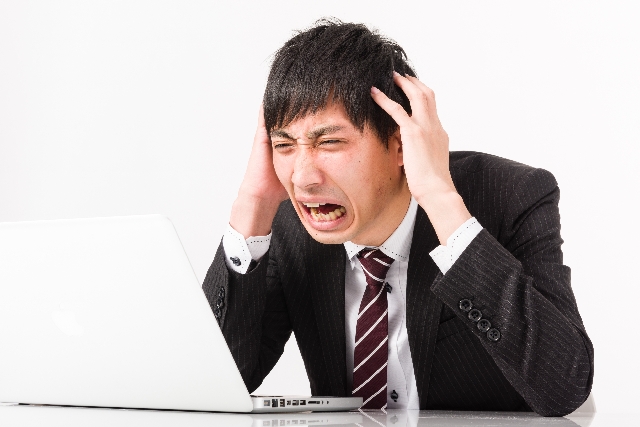「 報恩感謝 」

2月24日から始まったロシアのウクライナ侵略による戦争により、民間人にも多くの犠牲者が出ている状況で、日々心を痛めております。 被害に遭われた方々、残念ながらお亡くなりになられた方々に心よりお見舞いとご冥福をお祈り申し上げます。 今は、一刻も早く世界平和が戻ってくることを祈るしか出来ません。 日本は平和ですが、もう一つの脅威であるオミクロン株による第6波がピークアウトを迎えて、ようやく蔓延防止等重点措置も終了となりますが、いぜん予断を許しません。 そして、季節は三寒四温の中で、そろそろ春が近づいております。
そんな中、先月の2022年2月22日(800年に一度の2が続きの記念すべき日)に、東京にて東証一部上場企業にまで成長させた株式会社丸和運輸機関・和佐見社長とご面談頂きました。 2021年3月期には、売上高:1121億円 経常利益:82億円、今期決算では、1300億に達する素晴らしい業績で、皆さんも見たことが有るとは思いますが、トラックには桃太郎のイラストが描かれている大企業です。 1970年にトラック1台で起業をされてからの企業業績とパワーはもちろん素晴らしいですが、丸和運輸機関さんの“桃太郎文化”の奥の深さと「同音同響の経営」「報恩感謝」の意味を教えていただきました。 そして、阪神淡路大震災からのBCPへの熱い思いとパワーの源「商人道」とはの本質を学びました。 今週は、「同音同響の経営」と「報恩感謝」について学んでいきたいと思います。
“桃太郎文化”を大切にしていくということは、私たち一人ひとりがこの文化を共有することです。
※桃太郎文化参照
また、企業はさまざまな人々の集まりであるがゆえに、同じ目標のもとに互いを理解し、結束することが何よりも大切です。 私たちは、こうした企業としての一体感や心意気を最も重要と考えます。 そのうえで、社員を”同志的”な深いつながりをもった関係と捉え、「同音同響の経営」を実践しています。 同音同響の経営は、同志を尊重し、同志を大切にする経営です。 まずは、「同志第一義」の経営が基本です。同志の幸せなくして、会社の幸せはあり得ません。 同志を大切にし、同志の幸せの為にやり甲斐・働き甲斐のある職場環境をつくる。 そのことによって、同志一人ひとりのモチベーションがさらに高まり、会社も繁栄します。 1000年の永続的発展の実現は、働ける職場環境の整備と教育による、同志一人ひとりの成長に懸っているのです。 これを聞き、シューワグループとして至らぬ点、反省点に気付かされ、目先の利益に左右されずに事業本質の「なぜこのサービスが必要なのか」を定義づけをした中での「同音同響の経営」の必要性を強く感じました。 そして、和佐見社長が仰っていました社是「報恩感謝」です。
「報恩感謝」こそ幸福の基
生かされていることの自覚と、親、祖先を尊び、常に「ありがとうございます」の言葉を忘れずに。 報恩は、恩に報いること。恩返しをすること。 感謝は、ありがたいと思う心。 今の自分があるのは、たくさんの人のおかげであり、その恩に報いるような生き方をしたいと思う気持ちでしょうか。
特に、最近に感じることは、「恩を知る」とか「恩に報いる」ことを忘れた時代のように思えてなりません。 インターネット社会の中で、欧米的な権利主張が主流となり、日本人の古き良き時代の相手を思いやる「感謝」の気持ち自体が薄れているように感じます。 「報恩感謝」の心を持つことは人間にとってはきわめて大事なことで、人間は自分一人の力で生きているのではなくて、いわゆる天地自然の恵みをもらいながら人間生活に欠かす事の出来ない様々ものを与えられて生かされています。 「報恩感謝」とは報いる気持ち、”有難いと感謝する心”を現わす事を指す言葉であり、これが足りないからこそ”素直な心”も不足してしまうのかもしれません。 今考えてみても、若い時の自分に一番欠如していまっていた言葉と言っても過言ではありません。
冷静に考えると自然と心が高まっている人には、厚みがあるオーラが漂っていますし、自然とそれが表に出ています。 その一方では、いくら言葉で話していても、全くその様なオーラを感じない人もいます。 いかに感謝の気持ちをもってその人が生きているのか、オーラは人生の厚みである「報恩感謝」の結果だと学びました。
稲盛塾長の言葉に「心を高める、経営を伸ばす」と教えがあります。 我武者羅に数字にとらわれた経営をすれば一時は業績は上がりますが、事業は長続きはしません。 「利他の心」の心を学びながら、たくさん従業員と一緒に”物心両面の幸福の実現”を心から学ぶ組織風土で無ければ、無限の活力とでもいうものが湧き起こってくる組織にはなれません。 今回の「報恩感謝」の学びを通じて、「人の恩」を感じ、「感謝の心」を持ち「恩に報いる」ということの素晴らしさをお受けできたものと思っております。 これからも、さらに仕事を通じて「報恩感謝」の気持ちを持って人生に精進したいと深く感銘を受けました。 そして、この学びをより実践していかなければと強く感じました。