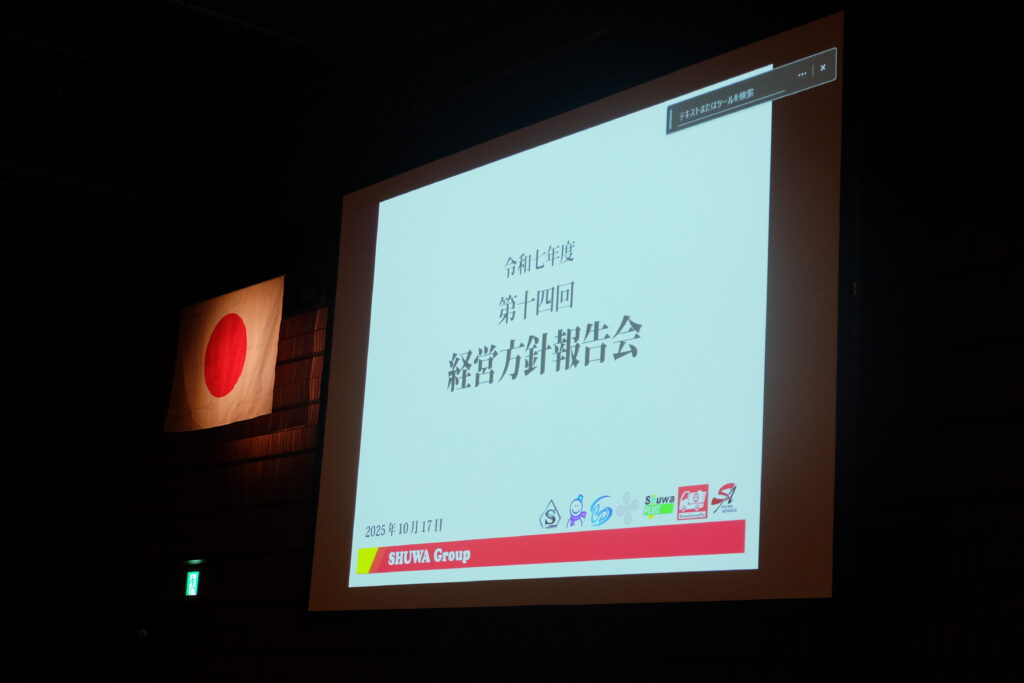変化対応力

昨今、シューワの中だけではなく変化対応力の重要性を説いているところが多くなっています。
この機会に、具体的にどのような力が必要なのかを調べてみました。
まず、文部科学省のホームページより「社会環境の変化と求められる人材像」という題名がありました。
その中で、各分野毎に求められる人物像を議論した時、いくつかの共通点があったということです。それは、
①当該分野の専門知識の土台となる基礎的な知識の徹底的な理解。
②産業のグローバル化に伴い、様々な人々と一緒に仕事をするための「グローバルな感覚」を持つこと。
※「グローバルな感覚」とは言語のみならず、自国の文化の理解や環境との調和の目線
③開発からサービスまで一連のバリューチェーンを俯瞰で見て遂行していくマネジメント力
④学んだ知識を現場に活用していくための能力として、「課題発見・解決力」「コミュニケーション能力」
これらの4つの点がありました。
また、人材紹介会社にリクエストのある企業が欲しがる人材についてですが、「社会が変わると求められる人材像も変わる」ということで、今のように時代の変化が激しいさまを「VUCA」と表現するそうですが、この言葉は、不安定・不確実性が高い・複雑・曖昧という意味を英語にした時の頭文字からなる言葉だそうです。
そして求められる人材像はまさに「変化への柔軟性がある」ということだそうです。
求められているスキルなどは社会の変化の中でこれから目まぐるしく変化することになり、絶対的に必要なスキルはある意味でないということです。
次に、「求められない人材像」ですが、これはウォーターフォール型でしか仕事ができない人材だそうです。
どういうことかと言うと、プロジェクトを工程に分け、確実に遂行していく手法だそうです。
変化に富んだ時代だからこそ、工程ごとに変化を受け入れることができなければ時代に合ったものはできないという見方が強くなっているのでしょう。
これらのように社会の変化に対して企業は柔軟に変化をしていかねばならず、そのために企業は「変化への柔軟性がある人材」を求めているということですね。
最後にこれから変わらずに持ち続けるべき力はあるのか?ですが、経済産業省において「社会人基礎力を持つ事」とあり、それには3つの能力が定義されていました。
①前に踏み出す力)(アクション)
・主体性:物事に取り組む力
・働きかけ力:他人に働きかけ巻き込む力
・実行力:目的を設定し確実に行動する力
②考え抜く力(シンキング)
・課題発見力:現状を分析し目的や課題を明らかにする力。
・創造力:新しい価値を生み出す力
・計画力:問題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
③チームで働く力(チームワーク)
・発信力:自分の意見をわかりやすく伝える力
・傾聴力:相手の意見を丁寧に聞く力
・柔軟性:意見の違いや立場の違いを理解する力
・状況把握力:自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
・規律性:社会のルールや人との約束を守る力
・ストレスコントロール力:ストレスの発生源に対応する力
これらの力は、時代が変化したとしても必要な力であるといえますから、この力の習得を目指していかなくては社会の一員として生き残ることが難しくなるかもしれません。
社員一人一人が変化に柔軟になった時、シューワという会社はこの激動の時代を悠々と乗り越えることができるかもしれません。
難しい時代だからこそ飛躍のチャンスがある。ピンチはチャンス!ということで頑張りましょう。